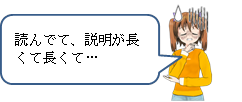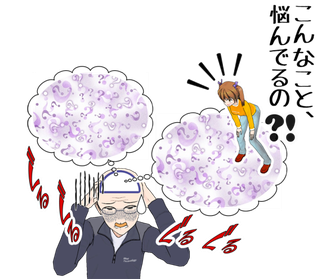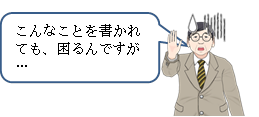- ホーム:第一部 まえがき
- 第2部 うつは 「治る」!
- 第3部 あなたは「新型うつ」である
- 第4部 だからあなたは「完治」しない
- 第4部の趣旨: 頭の中を整理しよう
- 第1章 うつの「特効薬」は「自分で作る」
- 第2章 「生活保護」でも「障害者年金」でもない選択肢
- 1)「メシが食えん」では食えません
- 2)人類の「メシの食い方」
- 3)現代日本の「メシの食い方」
- 4)「カネが無ければ食えません」
- 5)最小限度の「メシの食い方」
- 6)最小限度の制約①(自律支出:衣食住)
- 7)「カネが無くてはメシは食えない」のか
- 8)最小限度の制約②(他律支出(1):租税公課等)
- 9)最小限度の制約③(他律支出(2):扶養義務)
- 10)扶養義務との両立
- 11)人生での「リスク対処」
- 12)「雇用市場」で「メシを食う」
- 13)「雇用市場」のメカニズム①:需給の変動
- 14)「雇用市場」のメカニズム②:「必要性」と「能力」
- 15)「雇用市場」のメカニズム③:市場自身の有為転変
- 16)「雇用市場」が齎す「他律性」
- 17)「疑似問題」の先へ
- 18)【解①】「市場化原理」外での価値とは
- 19)【解②】「好きなことだけ」やる
- 20)【解③】「採算度外視です」
- 21)解①②③の結合
- 22)価値は「等価交換」
- 第3章 うつに向けられる「世間」の目
- 第5部 それじゃうつは「再発」する
- あとがき
- 自己紹介
- リンクとシェアについて
- おことわり
- サイトマップ
- 連絡先
4)うつの「原因」はこの「メカニズム」
(メカニズムの解剖とその評価)
「これは『普通』のこと」なのか
-
ここまで読んだら、こう仰る方もいらっしゃるかもしれない。
「これって、みんな『普通』のことじゃないか。
職場の『和』を乱さないように、職場の『しきたり』は全員が守る。
『上』からの指示に対しては、たとえどんなものであれ『一丸となって』従う。そして全員で『結果』を出す。
たとえその『結果』に実質的な内容が無くなっていても、『上』の人が満足できる『かたち』に作り上げる。
各自がそういう『工夫』をする。
こんなこと、みんなどこの会社でもやっていることじゃないか。何をくどくど書いているんだ」
と。
-
なるほど、確かに仰る通り「普通」のことなのかもしれない。
-
だがその「普通」のこととは、「ムラ社会」で「普通」のことだという意味だ。
「工夫」も「しきたり」も「和」も、全て「ムラ社会」で「掟」となっていることだ。
- それを「どこの会社でもみんな」などと言うのは、ご自分の「ムラ社会」の考えを「誰でも、どこでも」という意味に勝手に格上げしているだけのことである。
「普通のこと」はよいことか
- このような「『普通』のこと」は、所謂「グローバル化」で対抗してくる国外の競争相手に果たして通用するのだろうか。
- いや、日本国内であってもいい。
-
前記の通り、企業組織は経済合理性に合致している範囲内でしか存続を許されない。
「借金が返せなくなったら、会社は潰れます」という現実の前に、仰るような「『普通』のこと」をしていることが、どれだけ役立つのだろうか。
- 「これは、みんな『普通』のことだ」と仰る方は、その「普通」の意味をよくお考え戴きたいと思う。
「説明が長くて、長くて」
-
また、こう仰る方もいらっしゃるかもしれない。
「読んでいて、説明が長くて長くてくたびれました。
『ムラ社会』の話しだけでも、もう延々と続いていますよね。
どうしてこんなにくどくど、しつこい内容なのですか。」
などと。
-
もちろんうつになった人の全ての人(ここでは特に「新型うつ」の人)が、ここで書いた内容の全てを意識的に常時考えているとは限らない。
-
だが、もしかしたら無意識には、同じような考えが潜伏しているのかもしれない。
或いは、読んでから「そう言えば」と思い当たって、これから考えだすのかもしれない。
- それらの内容を出来る限り想定して書き出してみると、恐らくこういう内容になるのだ。
「思いもよらぬ」ことが悩み事
-
既に書いた通り、うつ病の原因は本人が内心で抱いていた何らかの価値観や価値の挫折若しくは喪失なのだ。
-
しかし「人は様々、十人十色」「三つ子の魂、百まで」なのだから、その価値観や価値は、人によって千差万別である。
これら病因に関する唯一かつ妥当な理由は、「本人にとって、(その時点では)それが最も重要なことだった」ということでしかない。 -
その病因の正否・適否・妥当性を、第三者が「値踏み」や「査定」をしてみても、無意味なのだ。
- つまりうつ病になった人は、周囲にとっては「思いもよらぬ」ことで悩んでいる。
- どういうことで悩んでいるのかある程度は察しがつく場合でも、それをどこまで「しつこく、くどくど」と悩んでいるのかは、傍目からは分からない。本人の頭蓋骨の中身が透けて見えるわけではないからだ。
悩み渦巻く頭の中
-
その意味では「どうしてこんなにくどくど、しつこい内容なのですか」という直観は貴重だ。なぜそう直感したのか。
-
それは、うつになった人の頭の中身を、ここでほんのちょっと垣間見たからなのだ。イラストに描いた通りだ。
- うつになった人の頭の中では、恐らくこんな悩みが渦巻いているのだ。
-
周囲にとって「思いもよらぬ」こととはどんなことなのか、またその「くどさ加減」は一体どんなものなのか。それを皆さんは一部体験なさった訳である。
- 皆さんはせっかくうつに関心を持って戴いて、読み始めて戴いているところなのだ。
- 最後まで読み終わった時点では、上記の直観はどのように変わっているのだろうか。是非最後まで読み終わってから、比べて戴きたいところである。
「こんなこと、困るんですが」
-
また、ここまで読んだ感想としてこう仰る方も、中にはいらっしゃるかもしれない。
「『ムラ社会』だの『要領』だの『掟』だの、こんなことを読まされても困るんだがね」と。
- なるほど、そのお気持ちはよくわかる。
- 既述の通り、「ムラ社会」の「掟」は不文律だ。
-
つまり、誰もが公然と口にするのを憚ることによって、「掟」と「ムラ社会」の価値を維持しているのだ。
懸命に努力して「ムラ社会」を維持しているただなかに、こうも身も蓋もない文章で「掟」の中身を明け透けに書かれてしまっては、立つ瀬がないということなのだろう。従って、中には困惑や当惑を通り越して、無礼と感じたり反感をお持ちになったりする方もいらっしゃるかもしれない。
「傾聴」の姿勢
-
だが皆さんはせっかくうつに関心を持って戴いて、読み始めて戴いているところである。
職場の同僚や部下や後輩の中には、うつになってしまった社員もいるかもしれない。
-
また、たとえうつを発症した社員が皆さんの職場からまだ出ていない場合でも、その可能性は避け得ない。
そしてその中には所謂「新型うつ」の場合もあるかもしれないのである。
-
そこで所謂「メンタルヘルスケア」の一環として、予防のため若しくはアフタケアの目的でそのような社員たちと面談することになるかもしれない。
その場合には、職場の代表なのだから、自分個人の価値判断は一時棚上げして、彼らの思考に付き合わなければならない。
所謂「傾聴」の姿勢が必要になるのだ。
事前準備の予期材料
- もし彼らの中に新型うつがあったらどうなるのか。ひょっとしたら彼らの内心には、ここでお書きしたような思考が渦巻いているのかもしれないのである。それに対して「そんなことを言われても困る」と言ったところで、面談相手の社員も困るだけだろう。
- 「話しを聞かせてくれ」と言われて面談した挙句に「そんな話しは困る」というのでは、何のために面談しているのか分からなくなる。
- だから面談に入ってからお互い困る前に、ここでお読みになった内容を予め片隅に入れておけば、その事前準備の一つにはなることだろう。
自制と理解のための練習台
-
いくら「そんな話しは困る」と拒否したところで、面談相手の価値観が変わるわけでもない。
「そんな価値観はけしからん」と怒ってみても、相手の頭の中身を他人が交換出来るものでもない。
-
それがたとえご自分にとってどんなに困惑や反感を余儀なくされるような価値観であっても、ご自分の視点から見て価値判断を加えることは、自制しなければならない。そうでなければ、相手の価値観に対する理解は生まれない。
- 繰り返しになるが、「ムラ社会」のメカニズムにしても「掟」にしても、ここでは価値観として肯定も否定もしているつもりはない。単に説明の対象として述べているだけである。
- 上記のような自制と理解のための練習台として、ここでの記述内容を是非ともご活用戴ければ幸いである。