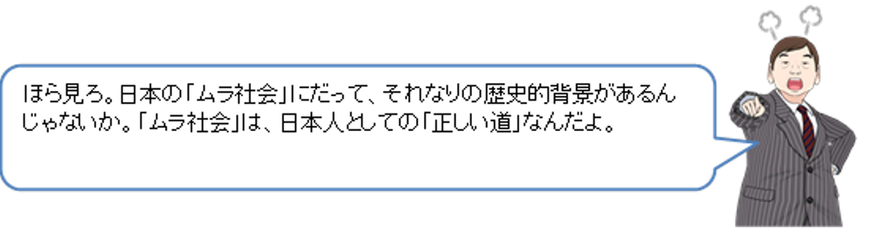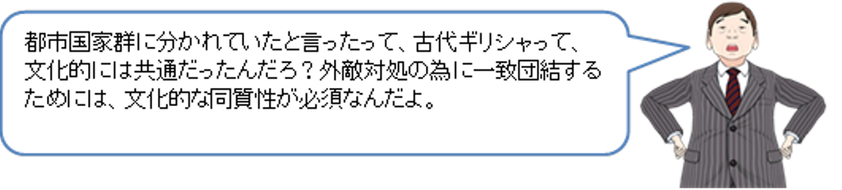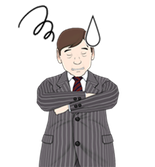- ホーム:第一部 まえがき
- 第2部 うつは 「治る」!
- 第3部 あなたは「新型うつ」である
- 第4部 だからあなたは「完治」しない
- 第4部の趣旨: 頭の中を整理しよう
- 第1章 うつの「特効薬」は「自分で作る」
- 第2章 「生活保護」でも「障害者年金」でもない選択肢
- 1)「メシが食えん」では食えません
- 2)人類の「メシの食い方」
- 3)現代日本の「メシの食い方」
- 4)「カネが無ければ食えません」
- 5)最小限度の「メシの食い方」
- 6)最小限度の制約①(自律支出:衣食住)
- 7)「カネが無くてはメシは食えない」のか
- 8)最小限度の制約②(他律支出(1):租税公課等)
- 9)最小限度の制約③(他律支出(2):扶養義務)
- 10)扶養義務との両立
- 11)人生での「リスク対処」
- 12)「雇用市場」で「メシを食う」
- 13)「雇用市場」のメカニズム①:需給の変動
- 14)「雇用市場」のメカニズム②:「必要性」と「能力」
- 15)「雇用市場」のメカニズム③:市場自身の有為転変
- 16)「雇用市場」が齎す「他律性」
- 17)「疑似問題」の先へ
- 18)【解①】「市場化原理」外での価値とは
- 19)【解②】「好きなことだけ」やる
- 20)【解③】「採算度外視です」
- 21)解①②③の結合
- 22)価値は「等価交換」
- 第3章 うつに向けられる「世間」の目
- 第5部 それじゃうつは「再発」する
- あとがき
- 自己紹介
- リンクとシェアについて
- おことわり
- サイトマップ
- 連絡先
4)「ムラ社会」は唯一の選択肢か
「ムラ社会」は日本人の「正しい道」か
-
さて前記の通り、日本が「ムラ社会」になったのは外敵対処の為に「鎖国」を目的としたためだったと仮説を述べた。
同質性の観念によって国家統一を図ったからだ、とも。
- では外敵対処の為に統一国家は本当に必要なのだろうか。
-
結論を先に言えば、外敵対処の為でも統一国家は不要なのだ。
まずは古代ギリシャを例にとって考えてみよう。
統一国家は外敵対処に必須か
【例①】 古代ギリシャの都市国家群とペルシア戦争
-
ご承知の通り、古代ギリシャは各々の「ポリス」、即ち分立する小都市国家の集合体だった。その時々で牛耳を執る有力都市国家が覇権を握ることはあっても、統一国家は作らなかった。
- だがペルシア戦争によって外敵の来襲を受けると、どうしたか。
-
降伏することを潔しとしない一部の都市国家群が結束して、大軍ペルシアの撃退に成功している。
統一国家の存在は、外敵対処のための必須条件ではないのだ。
-
因みに皆さんもご存知のアレクサンダー大王は、大統一王国を建設している。
だが大王の征服範囲は、所謂オリエント地方や西南アジアや中央アジア地域にまで及んでいる。ギリシャはその一部でしかない。 -
おまけに大王はペルシア戦争より百年以上も後世の人だし、そもそも出身地はマケドニア地方である。ここは当時としてもギリシャの中では辺境視されていた土地柄だ。都市国家群の「本土」出身ではないのである。
- アテナイだのスパルタだの、古代ギリシャの「本流」はあくまでも分立していた都市国家群の方なのだ。
- その例に見るように、統一国家なんか作らなくたって外敵対処は可能なのである。
文化の同質性は外敵対処に必須か
-
外敵対処に統一国家は不要だとしても、住民の一致団結と結束の為には同質性の観念を根拠にする必要があるのではないか。
こういうお考えの方もいらっしゃることだろう。 - また「古代ギリシャみたいな昔の話しではなく、現存の国家の事例でなければ現実味がない」と仰る方もいらっしゃるだろう。
- では今度はスイスを例に考えてみよう。
【例②】 スイス
-
アルプス山脈などの山岳地域一帯の住民が、外敵排除のために地の利を生かして一致団結の同盟を形成した。
大まかに言えば、この同盟が現在のスイス連邦の起源である。
-
だが、ご承知の通り「スイス語」なんて無い。フランス語・ドイツ語・イタリア語・レト=ロマン語の四言語が使われている。
宗教的にはカトリックもいれば、プロテスタントもいる。 -
つまり現在のスイスは、文化的には起源の異なる人たちが集まる、多文化社会なのだ。
-
しかしこのスイスは、ご承知の通り二十世紀の二度の大戦にも一貫して中立を維持し、永世中立策に拠って独立を維持している。
そればかりか金融業、製薬業、重電機械など、欧州有数の産業国家でもあって、その結果世界でも有数の生活水準を誇っている。
-
日常使っている言語がお互いばらばらだって、国民は皆「スイス人」として結束している。
文化の同質性なんかなくたって、一致団結は可能なのだ。
多文化共存は共和制か
-
それともここで、こう仰るのだろうか。
「多文化共存国家は、共和制によって人為的に作りあげた社会だ。君主制国家には当てはまらない」と。
それでは、君主制国家では多文化共存は不可能なのだろうか。 - これを現存の君主制国家であるベルギー王国を例に考えてみよう。
【例③】 ベルギー
-
ご承知の通り「ベルギー語」なんて無い。
ワロン系(フランス系)、フラマン系(オランダ系)、それにドイツ語系の各住民から成る一種の連合合作国家なのだ。 - 政治体制もややこしい。ワロン地域とフラマン地域の二つに首都区域を加えた三つの地域別政府を設け、更に言語別の共同体政府の別な三つを重畳させている。主な政党もワロン系とフラマン系それぞれに分かれて結成されている。
-
同質性どころか多文化分立、多文化並立の土地柄だ。
- だが建国以来一貫してベルギーの王家は一つである(ベルギーの王家は、もともとは中部ドイツ地方の旧サクス・コーブルク・ゴータ公国家の出身)。
-
王国だからといって、ベルギー国内にワロン王とかフラマン王とかいう地域別の君主がそれぞれいて、国内で覇を争っているわけではない。
国内に複数の異文化を包括しながら、王家も王位も首都も国家も統一されているのだ。
- おまけにベルギーは、イギリスに続いて二番目に産業革命が興った土地とされる。
-
従って、人口は千百万人余の小国ながら、今日でも欧州有数の生活水準を誇っている。
更に現在では欧州連合の本部所在地でもあって、外交上も一定の存在感を示している。
もちろんその間、国家の統一も王位の継承も一貫して維持しているのだ。
- 文化の同質性を国民に強制しなくたって、君主制国家の維持と形成は可能なのだ。
「ムラ社会」は唯一の選択肢だったのか
-
過去の日本において、「ムラ社会」化によって国民に文化的同質性を要求して鎖国したのは、確かに有り得る選択肢だったのかもしれない。
-
だが前述の事例三つで示した通り、他の選択肢を採った社会もあった訳だ。
そう考えると、日本が「ムラ社会」を選んだのは、当時としても必ずしも唯一の選択肢だったとは言えない。
- おまけにこの「ムラ社会」の選択肢は、社会に対して現実遊離の自己犠牲を要求する。
- その負担と効果を比較した場合、唯一の選択肢でもない上に、最善の選択肢だったと言えるのかどうかも分からないことだろう。
もはや「鎖国」はあり得ない
-
少なくとも今日では、「ムラ社会」の目的だった「鎖国」は既にあり得ない。
従ってこの「ムラ社会」化は、もはや現代の選択肢としては最善とは言えないだろう。
-
上記の通り、日本における「ムラ社会」は、たとえ外敵対処が目的であったとしても、唯一の選択肢ではない。
他にも選択肢があり得たからだ。それに関しては、既に幾つか国外の事例を挙げた通りだ。
-
また前記の徳島県海部町の例のように、日本国内にも全然「ムラ社会」ではない地域が現に存在している。
その意味でも、全然唯一の選択肢とは言えないのだ。
過去の偶然
- ましてや今日では、それは最善の選択肢でも何でもない。
-
偶々過去の日本列島に於いて、多数派住民が選んだ選択肢が「ムラ社会」だったというだけのことだ。
それ以上でもそれ以下でもない。
- 問題は必要に応じて社会原理を修正していくのか、それとも過去の歴史を理由に、現実遊離には目をつぶって今後も不変性に固執するのか、ということだ。
- 「日本人としての『正しい道』」などとは、とても言えないのである。