- ホーム:第一部 まえがき
- 第2部 うつは 「治る」!
- 第3部 あなたは「新型うつ」である
- 第4部 だからあなたは「完治」しない
- 第4部の趣旨: 頭の中を整理しよう
- 第1章 うつの「特効薬」は「自分で作る」
- 第2章 「生活保護」でも「障害者年金」でもない選択肢
- 1)「メシが食えん」では食えません
- 2)人類の「メシの食い方」
- 3)現代日本の「メシの食い方」
- 4)「カネが無ければ食えません」
- 5)最小限度の「メシの食い方」
- 6)最小限度の制約①(自律支出:衣食住)
- 7)「カネが無くてはメシは食えない」のか
- 8)最小限度の制約②(他律支出(1):租税公課等)
- 9)最小限度の制約③(他律支出(2):扶養義務)
- 10)扶養義務との両立
- 11)人生での「リスク対処」
- 12)「雇用市場」で「メシを食う」
- 13)「雇用市場」のメカニズム①:需給の変動
- 14)「雇用市場」のメカニズム②:「必要性」と「能力」
- 15)「雇用市場」のメカニズム③:市場自身の有為転変
- 16)「雇用市場」が齎す「他律性」
- 17)「疑似問題」の先へ
- 18)【解①】「市場化原理」外での価値とは
- 19)【解②】「好きなことだけ」やる
- 20)【解③】「採算度外視です」
- 21)解①②③の結合
- 22)価値は「等価交換」
- 第3章 うつに向けられる「世間」の目
- 第5部 それじゃうつは「再発」する
- あとがき
- 自己紹介
- リンクとシェアについて
- おことわり
- サイトマップ
- 連絡先
1)「メシが食えん」では食えません
「それじゃメシが食えないよ」
-
さてこれまでは「何のために生きているのか」という問題を検討してきた。
そこで人生観にどのような類型があるのか、幾つかモデルを列挙してきた。
もちろん、どの価値観もどの人生モデルも、どれを信じるのかは個人の自由だ。
- だが、ここですぐに出てくるのが「それじゃメシが食えないよ」とか「それはいいけど、どうやってメシを食うの?」という反問である。
-
つまり「なんだかんだ言っても、メシが食えなきゃ仕方がないよ」という議論である。
まことに仰る通りなのだが、しかしこの議論の展開には少々注意を要する。なぜか。
「バランスを取ればよい」のか
-
人生モデルの選択は、今後の人生をどう生きるのかと言う原則論の問題だ。一方「どうやってメシを食うのか」とは、その人生モデルを具体的にどのように実行するのか、その方法論の問題である。
つまり原則論の方が前提として先に存在する。方法論はその後に存在しているのだ。
-
だから、方法論を検討してみた結果が芳しくないからと言って、逆に遡って原則論を変更するわけにはいかない。
そんなことが簡単にできるようなら、そもそもそれは原則論とは言えない。単に、環境次第の便宜論だったということになるだろう。 -
だからこれは、「足して二で割って」対立点を中和できるような話でもなければ、「如何にバランスを取るのか」と言うような問題でも無い。
これが他の場合だったら「はい、そうですか。それではメシが食えないのですね」と言って速やかに回れ右が出来る。だが、ここではそうはいかない。なぜか。
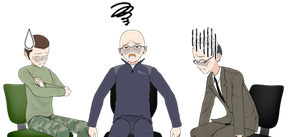
「逆戻り」しては「メシが食えない」
-
ここでは、ほかならぬ「如何にしてうつから脱け出すのか」を考えているところだ。
自分が内心抱いていた価値観に反する生き方をしていた結果、どうなったのか。皆さんは、とくに体験者の方は、うつという代償を払ってそれを身に染みて体験したところだ。 -
だからそうそう簡単に「メシが食えないからこの生き方はやめておこう」などと引き下がる訳にはいかない。
自分の価値観に反した人生を続けようとしたところで、いずれは破綻する。うつが再発して、それこそ元も子もなくなる。
また「すごろく」の繰り返しである。元の木阿弥に戻ったら、本当に「メシを食う」どころではなくなるのだ。
「メシを食う」とはどういうことか
-
自分の選んだ生き方を実現するためにはどうしたらよいのか。
その生き方なら、どこまで、どのような生活が可能になるのか。「窮すれば通ず」ではないが、なんとか活路が見出せるものなのか。 -
そのためには、少々事前準備が必要だ。そもそも「メシを食う」とはどういうことなのか。現代日本の社会ではそれは何を意味するのか。
先ずこれらの論点整理を予め行ってから、検討しなければならないのだ。

