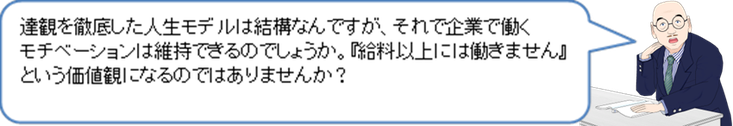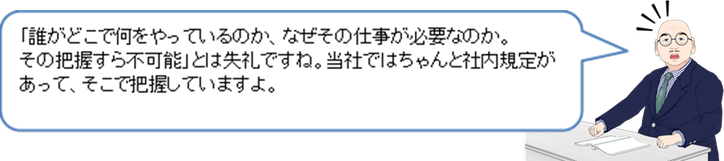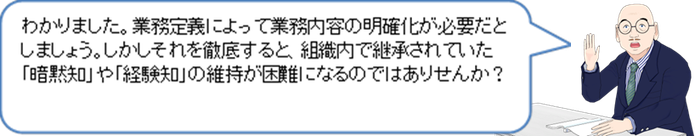- ホーム:第一部 まえがき
- 第2部 うつは 「治る」!
- 第3部 あなたは「新型うつ」である
- 第4部 だからあなたは「完治」しない
- 第4部の趣旨: 頭の中を整理しよう
- 第1章 うつの「特効薬」は「自分で作る」
- 第2章 「生活保護」でも「障害者年金」でもない選択肢
- 1)「メシが食えん」では食えません
- 2)人類の「メシの食い方」
- 3)現代日本の「メシの食い方」
- 4)「カネが無ければ食えません」
- 5)最小限度の「メシの食い方」
- 6)最小限度の制約①(自律支出:衣食住)
- 7)「カネが無くてはメシは食えない」のか
- 8)最小限度の制約②(他律支出(1):租税公課等)
- 9)最小限度の制約③(他律支出(2):扶養義務)
- 10)扶養義務との両立
- 11)人生での「リスク対処」
- 12)「雇用市場」で「メシを食う」
- 13)「雇用市場」のメカニズム①:需給の変動
- 14)「雇用市場」のメカニズム②:「必要性」と「能力」
- 15)「雇用市場」のメカニズム③:市場自身の有為転変
- 16)「雇用市場」が齎す「他律性」
- 17)「疑似問題」の先へ
- 18)【解①】「市場化原理」外での価値とは
- 19)【解②】「好きなことだけ」やる
- 20)【解③】「採算度外視です」
- 21)解①②③の結合
- 22)価値は「等価交換」
- 第3章 うつに向けられる「世間」の目
- 第5部 それじゃうつは「再発」する
- あとがき
- 自己紹介
- リンクとシェアについて
- おことわり
- サイトマップ
- 連絡先
2) 給料以上には働かない」のか?
「給料以上に働くのが当然」なのか
- 実は「『給料以上には働きません』という価値観の社員はおかしい」という価値観こそ、おかしい。これを裏返しに言うと「社員は給料以上に働くのが当たり前」という価値観だということになる。
- だがそもそも給与は仕事の対価なのだから、「何をいつまでに、どこまでやれば、いくらもらえる」という条件が明確でなければならないはずである。
タクシーとメーター
-
この考え方がおかしいという方は、ご自分がタクシーに乗った場合を考えてみればよい。運賃を支払ったあとで、訪問先で相手にこう憤慨してみせるのだろうか。
「酷いもんですなあー。今乗ったタクシーは、メーター以上に走ろうとしないんですよ」
などと。 - だがそんな憤慨をしたところで、「この人は一体なんのことを言っているんだろう」と怪訝な顔をされるだけだろう。
運転手のサービス
-
タクシーは、メーター計算の対価として運賃を得る。対価を請求するのは走り終わった時点だ。つまりメーターを倒したらそれ以上は走らない。
だからと言って誰もおかしいとは言わない。メーター以上は走らないのが当たり前だ。だからと言って運転手はそれ以上何もしないわけではない。 - 安全運転、滑らかな乗り心地、適切な空調と清潔な室内、合理的なルートの選択、目的地へ乗り付けるときのハンドルさばきの上手さ、手際の良い精算など、運転手が責任を負っている業務は多々ある。そのレベル如何でサービス品質が決まる。
- サラリーマンも同じだ。同じ業務内容が定義されていても、個人ごとの業務品質には差が出ることだろう。そこを評価対象にすればよいことだ。
仕事の「白紙委任」
- では、なぜ「社員は給料以上に働け」ということになるのだろうか。
-
日本では、就職と言えば「どの会社に入るのか」が目的だ。
「何をするために就職するのか」とか「入社してから何の仕事に従事するのか」などの問題は目的とされない。業務内容が定義されていないからだ。
では、なぜ業務内容を定義しないのか。
「負担」は青天井
- それは社員に対して無制限の負担を可能にするためである。
- 何しろ仕事の内容がはっきりわからないのだから、異動も転勤も急な配置転換も職務の内容変更も、自由自在だ。もちろん残業や休日出勤にも限度は無い。たとえ36協定などの法的規制があったとしても、それに対しては「決して表沙汰にしないこと」という「不文律」の「掟」を設けてしまえば、事実上制約は無くなる。もちろんそれではブラック企業になるわけだが。
-
社員は、このような無制限の負担に無条件に応じなければならない。もしかしたらこういう負担に耐えることが、その組織内では昇進や登用の条件になっているのかもしれない。既に書いたように「踏絵」と同じ機制である。
となると、これは社内銓衡に「暗黙の前提」として組み込まれているのかもしれない。でなければ、所謂「過労死」や「サービス残業」などは説明がつかないことだろう。
「暗黙の不文律」
- このような無制限の負担と「不文律」を当然のことと無条件に信じている場合、「社員は給料以上に働くのが当たり前」という価値観が生まれる。
- つまり「敢えて業務内容をはっきり定義しない」ことは、「暗黙のルール」であり「不文律」なのだ。もちろんその負担が不合理であればあるほど、「踏絵」として確実な選抜手段になることは既に述べた。
改善の可否
- 「日本企業のホワイトカラーは、生産性が低い」と問題視される。当然だ。どんな改善活動でも、第一歩は現状把握から始まる。ホワイトカラーが対象なら、先ずは業務分析だ。分析するためには、対象業務を明確化しなければならない。つまりは業務内容を定義しなければならない。
- だが「業務内容を定義しない」ことは「暗黙のルール」であり「不文律」なのだ。だから業務分析をすると言うことは、この「暗黙のルール」や「不文律」を破ることになる。こういう「掟」破りは、「ムラ社会」の最大のタブーである。従って、日本企業のホワイトカラーは業務分析が不可能である。
- 分析できないものが改善できるわけがない。「生産性が低い」どころか「誰がどこで何をやっているのか、なぜその仕事が必要なのか。その把握すら不可能」と言うのが実態なのではないのだろうか(この点について詳細は、次項で再説する)。
改善と分析の条件
- もし本当に生産性を上げたいのなら、前記のような「不文律」を放棄することだ。
- そうすれば業務分析も改善も可能になる。無駄がどんどん洗い出されてくることだろう。浮いた要員は他部門に転用してもよい。
- だが、この改善業務そのものでもいくらでも人手が必要だ。業務改善に終点は無いからだ。そして、どれだけ業務改善をできたかを評価すればよい。
業務の明確化と評価の運用
- 業務分析によって定義が明確化した業務はどうなるのか。定型化された業務だからといって、評価が固定されるわけではない。業務内容の定型化は評価の固定化ではないのだ。
- 業務内容に応じて、適切な業務品質の評価指標を開発して適用すればよい。タクシーの例で述べた通りである。
- 従って、業務と給与の対価関係を明確化したところで何も問題はない。いくらでも業務品質の評価方法はあり得るし、それによって働くモチベーションを維持促進する方法はあるのだ。
業務改善とモチベーション
- もちろんこんな業務改善などやらない方が、ある意味では楽である。何もせず、放っておいても社員が熱心に働くのなら、こんな楽なことはないことだろう。だがそんな組織で長年過ごしたらどうなるか。「『給料以上には働きません』という価値観の社員が出てくるのではないか」などと心配するのは、こういう人たちの台詞である。
- 要するに「給料以上には働きません」という価値観を「これ以上もう働きたくありません」という価値観だと勘違いしているのだ。
-
「給料以上には働きません」という価値観は、一体何を意味しているのか。著者に言わせれば、それは「これ以上もう働きたくありません」という価値観ではない。
それは「何をどこまでやれば、どのように評価されるのか。それをはっきりさせて下さい。そうしたらどこまで評価されたいのなら、何をどこまでやればいいのか、働く方で予め自分の見通しを立てられます。そうすれば、喜んで働きます」ということなのだ。
意欲喪失の原因
-
無制限の負担によって強いられる際限のない競争。それは何を生み出すのか。
競争には勝者と敗者がある。選抜試験には合格者と不合格者がある。勝者や合格者には達成感が生まれる。その代わり、敗者や不合格者には挫折感が生まれる。 -
つまり一部の意欲刺激と引き換えに、残りの一部には意欲喪失を生んでいるのだ。
従って「これ以上もう働きたくありません」という価値観を生んでいるのは、「給料以上には働きません」という価値観ではない。際限のない負担を強いるような制度そのものなのだ。 -
ではここで、そんな意欲喪失を生まないように企業が制度を改善したとしよう。
だがそれでも問題は残る。そもそも個人の価値観に他人が関与できるのかと言う問題だ。
職業観は個人の問題
-
うつ病から回復したあとで、社員の人生観がどのように変わったのか、変わらなかったのか。変わったとしたら、どのような部分がどのように変わったのか。
それはあくまで当人の問題であって、他人が口出しする問題では無い。ましてや職業観は、そのような人生観の一部でしかない。 -
社員には様々な事情がある。結婚、出産、育児、介護、家族親族との関係、家計の状態、健康などだ。
そしてそれらの事情は不変ではない。その時々で変化するし、異なってくる。それらを踏まえて、どこまで働く生活を選択するのかは、個人の判断の問題だ。 - どのような人生観で働くのかは個人の問題だ。それは社員に任せておけばよいし、他人が口出しする問題ではない。
- となると、企業が関与できる範囲はどこまでなのか。企業がやるべきことは何なのか。
企業側がやるべきこと
-
企業としてやるべきなのは、業務定義と評価方法の整備だけだ。もちろんこれには既に述べたような趣旨での「不文律」の放棄と業務分析が前提になる。
そしてその業務定義と評価方法にしたがって、優れた成果を挙げた社員は評価し、そうでなければ努力を促す。それだけのことだ。 -
そして、対価として支払った人件費総額と企業の年間業績が見合っていればよし、そうでなければ見合うように業務定義と評価の方法を修正する。
企業にとって取り組むべきなのは、この費用対効果の方なのだ。利益を生むのが企業の目的だからだ。
-
同じ人件費総額を支出するならば、その引き換えとしてできるだけ多くのアウトプットを得なければならない。
そのためには組織と制度とその運用を改善する。それによって社員の意欲と成果の達成を誘導する。これまでにも諸々述べてきた通りだ。 -
企業としてやるべきなのは、それだけなのだ。
社員がどのような職業観を持っているのか、わざわざ心配する必要もなければ、「社員が給料以上に働かない」などという杞憂に陥る必要もないのだ。つまりはこれも「疑似問題」なのだ。
業務の定義とは
- 「誰がどこで何をやっているのか、なぜその仕事が必要なのか。その把握すら不可能」とは一体どういう意味なのか。
- もちろんどの企業にも組織図があり、大まかな職務分掌規程はあることだろう。「『把握すら不可能』なんてとんでもない。ちゃんと社内規定があって、そこで把握している」という反論もあることだろう。
「会議」とは何か
- だがそう反論する前に、ちょっと考えていただきたい。
-
例えば目の前で開催されている会議だ。
これは一体何のために会議しているのか。「以前からの引き継ぎで」からか。それとも「定例だから」か。それでは門松や節句や中秋の月見のような年中行事ということなのか。
会議は社内の「風物詩」なのか。
「情報共有」機能
- それでは会議の目的は「情報共有」のためなのか。
-
それならその会議で出された情報は、会議の出席者がその場その時点で全員必要なのか。そうではあるまい。
それなら、必要な情報を必要な人が必要な時に入手できるような仕組みを考えた方がよい。いちいち出席者全員の時間コストを消費する必要はない。 -
それともこう反論するのだろうか。
「情報の需要者が取りに行くだけでは、時期も逸するし内容も不足する恐れがある。情報の需要が不明な時点でも、情報の保有者が組織内の全員に事前に展開しておく必要があるのだ」
と。
「適時適所」の制度化
-
だが要否も不明な情報のために、出席者全員の時間コストを消費するのでは無駄が大きすぎる。
それよりは、情報の保有者が、情報の需要者に対して自発的に情報提供するような仕組みを考えた方がいい。
他部署や他の社員にとって役に立つ情報を「これ、知っておいた方がいいんじゃない?」と自ら提供したら、何らかの評価を加点する。しかもその情報提供が絶妙のタイミングだったら、一層評価を上積みする。こんな仕組みだ。 - もちろん提供された情報の内容を吟味することは、評価の当然の前提だ。誰でも知っているような情報とか、どこでも入手できるような内容だったら評価はしない。
-
だが需要者にとっての情報の価値は、たとえ同じ内容だったとしてもタイミングによって時々刻々変わる。
従って、そのような情報の「時間価値」も考慮して評価すれば、情報提供の自発性ばかりではなく、そのタイミングも内容も適切に制御できることだろう。
「意思決定」機能
- それとも会議は「意思決定」のためなのか。
-
それなら意思決定権者が、関係者から説明を聞いて一人で決断すれば済む話だ。それを会議でいちいち出席者全員に聞かせなければならないというのは、どういうことなのか。
その決定事項が、組織内の誰にとってどこまで影響が及ぶのか、その事前把握ができていないということなのではないのか。
「ムダ会議」の退治
- だから、そもそも会議そのものを「不必要悪」とする必要がある。「必要悪」ではない。「そもそも不要なもの」と言う意味である。そのためにはどうしたらよいのか。
-
出席予定者全員の出席予定時間を総合計して、その合計時間をコストに換算しておく。
そしてそのコストは、意思決定権者つまり組織の長の職務に対する事前ペナルティとして、負担させておく。
組織の長として自分が主宰する、会議の時間と出席人数と回数。その総合計が事前ペナルティになる。
だから会議を減らせば減らすほど、評価が上がる仕組みだ。
「退治」から得られるもの
-
そうすれば、目的がたとえ情報共有だろうと意思決定だろうと、組織の長が先頭に立って必死に会議を減らすことだろう。
情報共有や意思決定は会議以外の方法で実現すればよい。 -
そうすれば会議の機会は極限まで減り、どうしても必要な最小限の会議だけが残ることだろう。
その最小限の会議コストだけは、組織の長に課する事前ペナルティから除外しておけばよい。税金ではないが、謂わば「基礎控除」というわけだ。 -
こうすれば、それまであちこちの会議に消費されていた社内の時間がいっぺんに浮く。
その時間は、これまでの業務の改善にも、新たな業務の取り組みにも向けられる。
「時間」だけは平等
-
企業によって資金力や規模の大小の差はある。
だが、どんな企業でも「時間」だけは平等にある。市場競争で先行優位にある企業をキャッチアップするためには、後発企業にとっては「時間の使い方」を変えるしかないはずだ。会議ひとつとっても上記の通りなのだ。 - もちろんここで述べているのは著者の仮説に過ぎない。
-
だが、その業務はなぜ必要なのか、その必要性をどこまで自覚的に明確化できているのか。より少ないコストで同等の業務が実現可能ではないのか。本当にそのような代替手段はないのか。そのような代替手段実現のために、何か制度的な改善をしているのか。
その答えを「業務規定があるから」で済ますのでは、どんな組織改革も経営革新もできない。捉われることなしに、上記のような疑問を常時しつこいほど考えていなければならないのではないのだろうか。 - 「その把握すら不可能」とは、果たしてこういうことをちゃんとしているのかどうか、という意味である。
「暗黙知」とは何か
- 「『暗黙知』の継承が心配になる」とは、実はそもそも自己矛盾の表現である。なぜか。
-
企業が把握していない内容が暗黙知なのだ。
従って「暗黙知を維持しなさい」では、そもそも業務命令として成り立たない。把握していない対象を指定して業務命令を下すことはできないからだ。つまりはこれまた「疑似問題」である。
ではどうしたらよいのか。ちょっと考えてみよう。 -
因みに予めお断りしておくと、著者はもとより専門家ではないし、ここで述べている内容にしても職務上の体験がある訳でも、自分の実体験がある訳でもない。実例として挙げている訳でもない。内容としては全くの仮説である。
だから、この仮説に従えば暗黙知や経験知が継承されると保証している訳でもないし、況や推奨している訳でもない。あくまでも個人的な仮説に過ぎないことをお断りしておく。
維持の方法
-
さて、企業が把握していない内容が暗黙知だ。従って企業は、暗黙知や経験知の維持自体を直接図らなくてよい。企業としては、暗黙知や経験知に対する評価方法だけを制度化すればよいのだ。例えば下記の通りだ。
-
- 暗黙知や経験知そのものの評価(蓄積の評価)
- 暗黙知や経験知を記録したことの評価(明文化の評価)
-
暗黙知や経験知を展開したことへの評価(共有化の評価)
-
このような評価方法の制度化は、暗黙知や経験知の継承と維持が自発的に行われることを促進するためだ。
だがそれには一定の条件がある。
前提条件
-
最初の前提条件は、単なる思い出話や手柄話や自慢話などはもちろん評価しないということだ。
職場内の若手を掴まえて、年長者が何時間も自慢話を聞かせた挙句に「これだけ『経験知』を継承しておきました」などとドヤ顔で点数稼ぎに来られても困るからだ。 -
では先行世代の暗黙知や経験知は、どのようにして評価するのか。
それは、若手からの評価に拠らなければならない。
- 無記名アンケートをとるのか。普段から何くれとなくアドバイスをくれていることへの口コミか。自由参加で課外講義をしてもらって、その出席率と人数によるのか。
- いずれにせよ、後続世代からどれだけ評判を勝ち得ているのかが、暗黙知や経験知の価値になるのだ。
-
またもう一つの前提条件は、評価は加点主義とするということだ。
ノルマや目標を設定して強制したり競わせたりしてはならない。暗黙知や経験知の自発的な共有化を促進するためだ。
組織上の条件
- 実はこの加点主義の実現には、更に組織的な手当てを必要とする。どういうことか。
- 横並び一直線の中で、相対評価によって差をつけるような評価制度や昇進制度。組織全体の数値目標は、頭数で割って均等配分する。まるで「人頭税」のような目標管理制度だ。
- このような組織内では、暗黙知や経験知の共有は不可能だ。職場内の同僚は、同列線上で評価を争うライバルなので、手の内は明かさない方がトクだからだ。
-
したがって暗黙知や経験知の共有のためには、このような横並び競争を前提とした組織をあらためなくてはならない。そして役割分担型の組織に再編成した上で、個別的評価制度の導入が必要になる。例えばこんなイメージの組織になることだろう。
-
- 数値目標の達成責任はチームの主宰者つまり管理職が負う
-
メンバーに対しては、チームプレーを定義し、プレーヤーごとの役割を定義し、チームプレーを組み合わせてチームの戦術や戦略などを規定する
-
このようにして、組織を役割分担型に再編成する。そしてプレーヤーの役割ごとに個別の評価制度を設ける。
暗黙知や経験知の共有という目的のためには、組織原理と人事評価制度に関してこのような改善が必要になるのだ。 -
もちろん、暗黙知や経験知の共有と継承は、常時継続されなければならない。
明文化や共有化は一度ポッキリでは終わらない。時間の経過とともに、環境の変化も事業内容の変遷もある。従って暗黙知も経験知も新たに蓄積されていく。
また時間の経過は、世代交代も齎す。従って暗黙知や経験知の共有と継承の為には、不断の努力が必要なのだ。
問題の所在
- 以上のように、暗黙知や経験知の共有と継承のためには、組織や制度に関して一定の手当てと努力が必要だ。何もしなくても、何かが得られるということは有り得ない。放っておいても、暗黙知や経験知が共有されたり継承されたりするわけではないからだ。
-
組織内で継承されていた「暗黙知」や「経験知」の維持が困難になるのは、業務内容の明確化が徹底するためなんかではない。
暗黙知や経験知の共有と継承のためには組織や制度の手当てが必要なのに、それをしていないためである。 - そのような手当てをしていない企業が、暗黙知や経験知の維持を憂えるのはおかしいのだ。そもそも企業が把握していない内容が暗黙知なのだから。何もしていない企業は、そもそも社内にどれだけの暗黙知や経験知が維持されているのか、把握しようがない。
-
もしかしたら何の暗黙知も経験知も、維持されていないかもしれない。そのことすらも把握しようがないはずである。
もっとも「現在でも『暗黙知』や『経験知』が社内で維持されている筈だ」という期待を抱いている企業もあるのかもしれない。だがもしかすると、その期待は単なる幻だったのかもしれないのだ。
懸念の背景
- 「業務定義によって業務内容の明確化を徹底すると、組織内で継承されていた『暗黙知』や『経験知』の維持が困難になる」という懸念。この懸念は一体どこから生じているのか。
-
業務定義によって業務内容の明確化を徹底すると、誰がどこで何をどこまでやるのかが明確になる。
当然その中に「暗黙知」や「経験知」の維持について含まれているのかどうかも、明確になる。もちろん他のことなら、業務定義に漏れがあればそれを追加すれば済む話だ。 - だが企業が把握していない内容が暗黙知なのだ。だから「暗黙知を維持しなさい」という業務定義は追加のしようがない。
-
暗黙知とは一体何なのか。また、その維持のためには企業の組織や制度をどう改善したらよいのか。
もしもその企業がそのために必要な手当てをしていなかった場合、全てをゼロから始めなければならない。
その負荷の大きさを前にして感じる躊躇。そんな躊躇が、この懸念の背景にあるのではないのだろうか。
開けてしまった「パンドラの箱」
-
つまり「業務定義によって業務内容の明確化を徹底すると」失われるのは「暗黙知」や「経験知」ではない。
「現在でも『暗黙知』や『経験知』が社内で維持されている筈である」という「幻の期待」の方なのである。 - もっとも「暗黙知」や「経験知」が全く維持されていないという場合ばかりではないだろう。その場合は「現在でも『暗黙知』や『経験知』が社内で維持されている筈である」という「期待」はあるのかもしれない。
-
だが、もしかしたらその『期待』は『幻』に終わる可能性だってある。既に書いた通りだ。
そうなると、知らなかった方が幸せだった「不都合な真実」を知ることになる。謂わば「パンドラの箱」を開けてしまった訳だ。
「不都合な真実」とは
-
だから、この懸念を正確に言えばこうかもしれない。
懸念しているのは「暗黙知」や「経験知」が失われることなんかではない。寧ろ、この「パンドラの箱」から現れるかもしれない「不都合な真実」の方なのだ、と。